はじめに
親のイライラ爆発前に、遊びでアプローチしませんか?
「朝、全然起きてこない…」「夜はなかなか寝ない…」
夏休み、よくあるお悩みですよね。特に子どもが小学生くらいになると、自分のペースで生活する力が育ち始める一方で、学校のような“外からの枠”がなくなると、生活リズムが崩れやすくなります。
でも、だからといって「早く寝なさい!」「なんで起きられないの!」と怒るだけでは、逆効果。
今回は、療育の専門家として、「遊び」を通して生活リズムを整えるコツをご紹介します。親も子も楽しく取り組める工夫が満載です。

夏休みの生活リズムが崩れるのはなぜ?
子どもの生活リズムが崩れるのには、いくつかの理由があります。
- 朝の“登校目標”がなくなる
- 夜にスマホやテレビなどの刺激が多い
- 家族全体の生活ペースが遅くなる
- 子ども自身に「時間の感覚」がまだ育っていない
特に年齢が低いほど、「時間」という概念はぼんやりしています。
まずは「どうしてこうなるのか」を理解することが、対応の第一歩です。

★親の「注意→反発」パターンを断ち切るには
「また寝坊して!」「何時だと思ってるの!」
…そんな声かけ、つい言ってしまいませんか?
子どもは「怒られる=関わってもらえた」と感じることもあり、注意されることで逆に“無意識の行動強化”になることも。
また、頭ごなしの否定は自己肯定感を下げ、生活リズムの回復にも逆効果です。
代わりに、
- 「今は朝のおしたくタイムだね」
- 「昨日より5分早く起きられたね!」
など、時間や行動を具体的に示しながら、できたことに目を向ける声かけが効果的です。
効果的にほめる5つのポイントが記載されているそらまめキッズのInstagramもぜひご覧ください♪
🌟ママ必見!これでOK!伸びるほめ方5ポイント🌟

子どもに響く“遊びベース”の生活リズム改善術
では、実際にどんな「遊び」でアプローチできるのでしょうか?
以下に、支援の現場でも効果的なアイデアをご紹介します🌟
★時計遊び:時間の“感覚”を育てる
アナログ時計とタイマーを活用して、時間を「見える化」しましょう。
たとえば、アナログ時計に「時間の目印シール」を貼って、
- 朝7時には短針のところに「朝ごはんマーク」
- 朝8時には長針のところに「おしたく完了マーク」
をつけておくと、「この時間になったらご飯だね」「もうすぐ準備の時間だよ」と、目で見て“時間の流れ”を理解しやすくなります!
100均のシールや、親子で描いた絵でもOK!“時間=行動”のつながりを楽しく覚える工夫になります☆彡

★「おしたくビンゴ」や「朝ミッション」ゲーム
朝のお支度や夜の行動を“ミッション”として楽しみます。
- 起床 → 顔を洗う → 着替える → 朝ごはん → 出発準備
をビンゴやチェックリストにして、1日1スタンプ!
「全部できたらシール1枚」「3日でおやつゲット」など、ごほうびを用意するとやる気もアップします。

★支援現場でも使われる“ごほうび表”の工夫例
子どもの特性によっては、「視覚的な刺激」が有効な場合があります。
- 自分専用のカレンダーにシールを貼る
- 親子で選んだ「週末の楽しみ」が待っているようにする
- 「自分で決めたことを守れた!」という達成感を大切にする
療育の現場では、「できた!」を積み重ねていくことで、行動の安定につながることがよくあります。

「つい夜更かし」に効く!夜の過ごし方アイデア
夜のダラダラ時間は、朝の寝坊の大きな原因に( ;∀;)
- ブルーライトを減らす(夜8時以降は画面タイム終了)
- 部屋の照明を暖色系に
- お風呂→読書→ストレッチ→おやすみ…という流れを習慣化
してみるのもよいかもしれません✨
4つのアイデアをお伝えしますね♪

📚 読み聞かせストレッチ
おやすみ前に、布団の上で親子でできる簡単ストレッチに読み聞かせを組み合わせたものです。
お話の登場人物になりきって体を動かす(例:「くまさんがのびをして…ママも一緒にぐーん!」)
「ぞうさんが深呼吸〜。すーっ、はーっ」と呼吸をゆっくりする
絵本に合わせて寝転んで手を広げる、足を伸ばすなど
心も体もリラックスすることで、自然と“おやすみモード”に切り替わります。
🌟 星を探すごっこ遊び
「ねる前のおたのしみ」として、部屋の明かりを少し暗くして、
「今夜のお空に星が出てるかな?」と天井を見上げる
天井や壁に貼った蓄光シールやLEDライトを「発見!」して喜ぶ
「あれはお母さん星」「あれは今日頑張ったごほうび星だね」と、親子で空想の世界を楽しむ
スマホやテレビではなく、“ゆったり静かでワクワクする時間”が眠りへのスイッチになります。
🐢「ぬいぐるみおやすみ劇場」
子どもが大好きなぬいぐるみを主役にして、
「○○くんがねむくなってきたよ〜」と声を変えて演じる
お布団をかけて「トントンおやすみ」を一緒にする
“ぬいぐるみが眠る=自分もそろそろ寝る時間”という感覚が育ちます。
🎵「音あてクイズ」
明かりを消したあとに、耳を澄ませて静かな音を楽しむゲームです。
「今の音、なんだった?」「外で車が通った音かもね」
「じゃあ次はママが静かに○○する音をあててね」
視覚ではなく“聴覚に集中する”ことで、自然と眠気を誘いやすくなります。

まとめ
楽しく取り組めば、夏休み後の朝も笑顔に!
生活リズムを整えるのは、親にとっても子どもにとっても大きなチャレンジ。
でも、“怒る”“注意する”ばかりではなく、「遊び」や「楽しさ」で取り組むことで、自然と整っていく力が育ちます。
夏休みは、子どもが自分のペースを試す貴重な期間。
親子で一緒に楽しみながら、笑顔で迎える夏休み明けを目指しましょう!
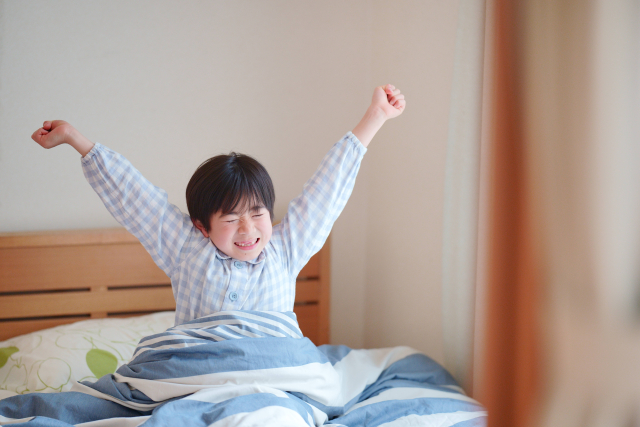
 Instagram
Instagram
 TikTok
TikTok
 Note
Note
 Facebook
Facebook










