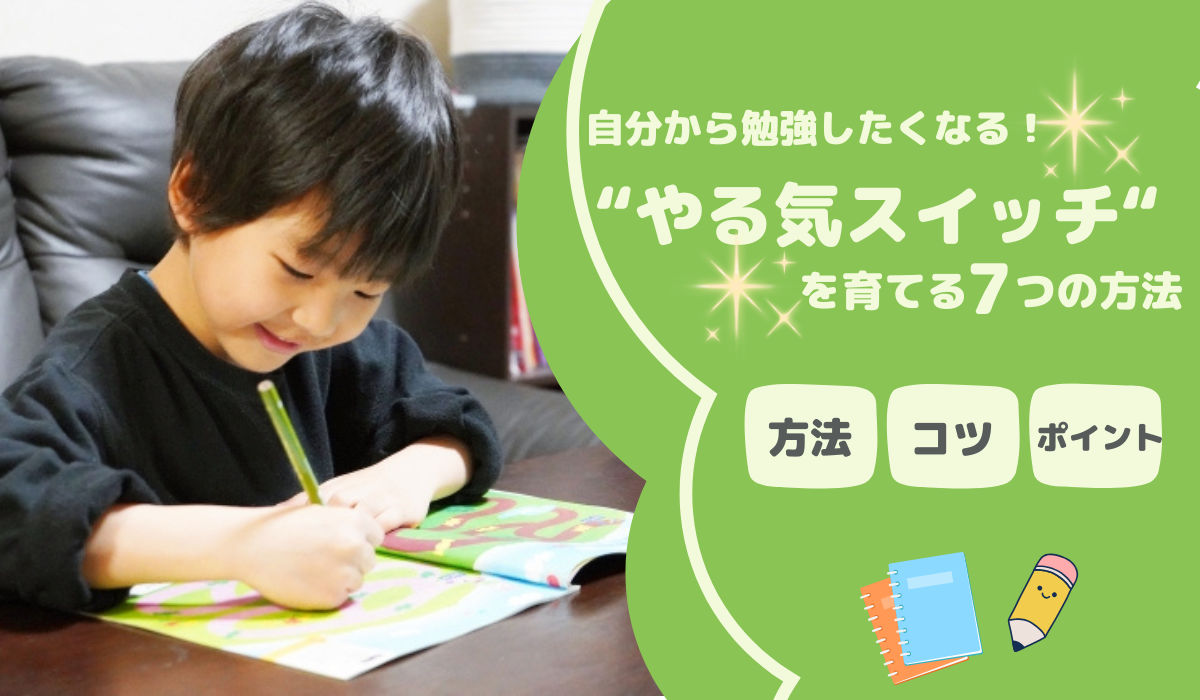はじめに:うちの子どうして勉強しないの?
「うちの子、全然勉強しないんです…」
子育て相談で多い悩みの一つです。
どんなに「勉強しなさい!」と言っても、子どもはなかなか動かない。
それどころか、言えば言うほど反発してしまう──そんな経験はありませんか?
実は、“やる気”とは「気合い」ではなく、「安心感」と「成功体験」から生まれるもの。
押すのではなく、育てるものなのです♪
この記事では、療育の現場で数多くの子どもたちと関わってきた専門家の視点から、
小学生が自分から勉強したくなる“やる気スイッチ”を育てる7つの方法を紹介します✨
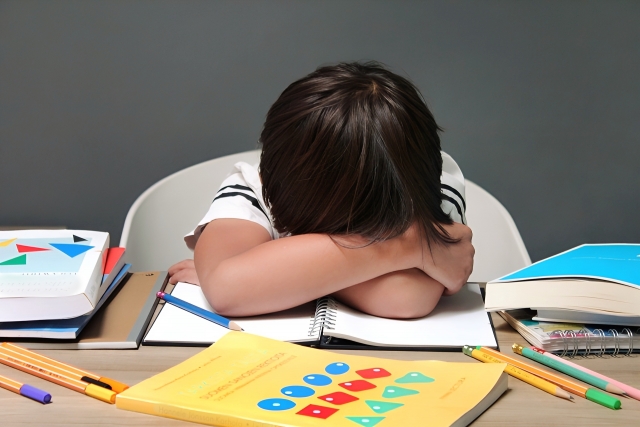
そもそも「やる気」ってどこから生まれるの?
子どものやる気は「努力」ではなく「環境」と「感情」から
「やる気がない」と言っても、子どもの脳の中では“やる気スイッチ”が眠っている状態です。
それを押すのは、「楽しい」「できた!」というポジティブな体験。
つまり、やる気の正体は感情と報酬にあります。
「できた!」と感じる瞬間に、脳が“またやりたい”と感じる。
だから、子どもにとって“成功体験”を積み重ねることが最初の一歩です。
「やる気が出にくい子」の特徴
- 指示の理解が苦手
- 見通しが立ちにくい
- 注意が逸れやすい
- 失敗体験が多く、自信をなくしている
そんな子どもたちは、“やる気”の前に“安心”を必要としているのです。
だからこそ、「無理にやらせる」より「できそうな入口を用意する」ことが大切です(#^^#)
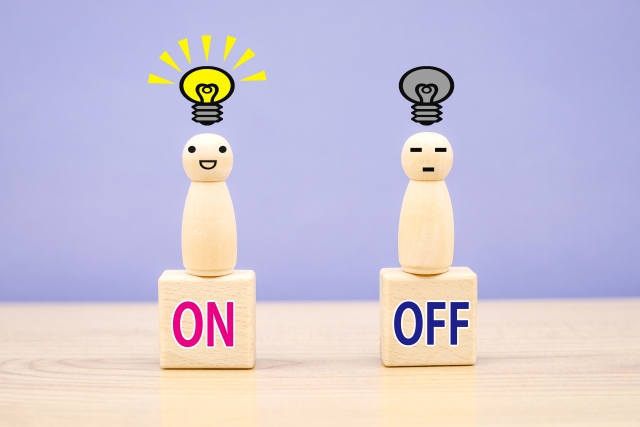
やる気スイッチを育てる7つの方法
① 小さな成功を積み重ねる「スモールステップ」
いきなり「宿題全部やろう」はハードルが高すぎるかも…。
最初は「1ページだけ」「5分だけ」でOK✨
「できた!」を積み重ねることで、“またやりたい”という気持ちが自然と生まれます。
小さな目標を達成するたびに「できたね!」と一緒に喜びましょう♪
② 自分で選ばせる「選択制学習」
「今日は算数と国語、どっちからやる?」
「5時と6時、どっちにやる?」
子どもに“選択権”を与えることで、自主性と自信が育ちます。
自分で決めたことは続けやすい。
選ぶことで「自分で決めた」感覚が生まれ、やる気が長続きします!
③ “見える化”でモチベーションを支える
勉強量や達成度を見える化することで、「頑張ってる自分」を実感できます。
シールカレンダーや「やる気メーター」を記録するのもおすすめ。
できた課題をボードに貼っていくだけでも、“達成感”が子どもの脳を刺激します。
④ 「ほめるフィードバック」で伸ばす
「よく頑張ったね」「丁寧に書けてたね」。
過程を認める言葉がやる気を育てるカギです。
★NGワード:「なんでこんなこともできないの?」は自信を奪ってしまい、子どもはやる気をなくしてしまいます💦
⑤ 勉強しやすい環境を整える
やる気は「場所」でも左右されます。
照明・温度・姿勢・周囲の音、すべてが集中力に影響します。
★感覚過敏や多動傾向のある子には、環境調整が必須。
- 背中が安定する椅子
- 不要な刺激を減らす(机の上はシンプルに)
- 消しゴムや鉛筆を複数置かない
⑥ 声かけ・関わり方を変える
声のかけ方ひとつで、やる気は大きく変わります。
NG:「早くしなさい!」 → OK:「どこまでやる?一緒に考えよう」
★おすすめの“促しの3ステップ”
- 共感する(「やりたくない気持ちも分かるよ」)
- 提案する(「じゃあ5分だけやってみようか」)
- 選ばせる(「どっちのノートからにする?」)
⑦ 自己肯定感を育てる関わり
「やる気の根っこ」は自己肯定感です。
できないことより、できたことに目を向けましょう。
★「褒める」「認める」ことが大切。
「頑張ったね」「ここまで自分でできたね」と行動を具体的に言葉にします。
失敗しても、「うまくいかなかったけど、チャレンジしたね」と伝えましょう◎

家庭でできる実践ステップ
Step1:1週間の“やる気チェックシート”を作ろう
「今日のやる気度」を10段階で記録するだけでも、
子どもの自己理解が深まり、親も声かけのタイミングを掴みやすくなります。
- 朝:やる気メーター(1〜10)
- 夜:今日のがんばりメモ(「〇〇をがんばった!」)
Step2:親子で1日5分のふりかえりタイム
寝る前や夕食後など、1日5分でOK。
「今日できたこと」を3つ書き出してみましょう。
この“振り返り”が自己効力感を高めます。
親が「一緒に書こう」と誘うと、子どもは安心して取り組むことができます♪
Step3:継続できたら一緒に喜ぶ
「続けられたね」「昨日より早くできたね」など、
成果を共有することで、親子の信頼関係も強化されます。
★やる気の源は「親とのつながり」

やる気が出ないときのリセット方法
「やらない日」も責めない
誰にでも「やる気が出ない日」はあります。
“今日は充電する日なんだね”と受け止めるだけで、
子どもは自分を否定されず、次に向かう力を取り戻します(^^)/
気持ちを切り替えるための小さな工夫
- 深呼吸や軽いストレッチをする
- お茶や水を飲んでリセット
- 机の上を片づける
- 音楽を変える
再起動のきっかけは「体の動き」から♪
“心を動かす”より、“体を動かす”ほうがスムーズなことも◎

保護者が覚えておきたい「NG対応」
- 「勉強しなさい!」(命令型)
- 「お兄ちゃんはできたのに」(比較)
- 「100点じゃなきゃダメ」(結果重視)
- 「いい加減にしなさい!」(感情的)
これらはすべて、やる気を削ぐNGワードです。
★親は「叱る人」ではなく「伴走する人」に
子どもと同じ方向を向いて「一緒に頑張ろうね」と伝えてみましょう✨

まとめ:やる気は“押す”ものではなく“育てる”もの
勉強へのやる気は、言葉で押し込むものではなく、
「できた!」を積み重ねる中で自然に育つ力です。
親ができることは、
子どもが自分で進みたくなる環境と関係性を整えること。
そして、やる気が出ないときも責めずに「次に繋がる小さな成功」を支えることです。
「やる気が出ない子」ほど、伸びしろをたくさん持っています。
焦らず、比較せず、子どもが“やりたい”と感じる瞬間を一緒に探していきましょう。
その一歩が、未来の大きな学びにつながります(*^-^*)
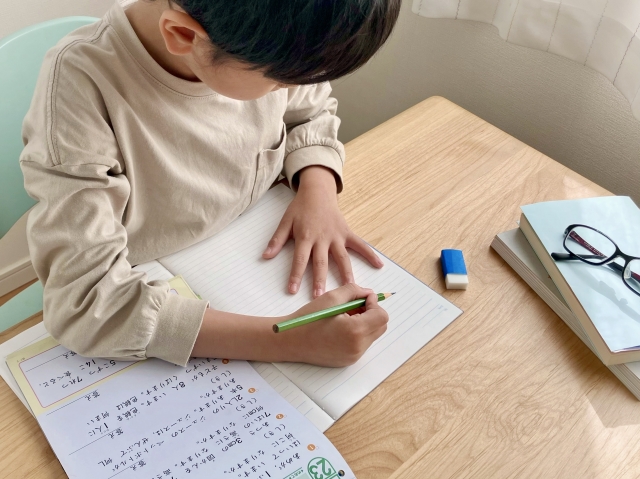
 Instagram
Instagram
 TikTok
TikTok
 Note
Note
 Facebook
Facebook