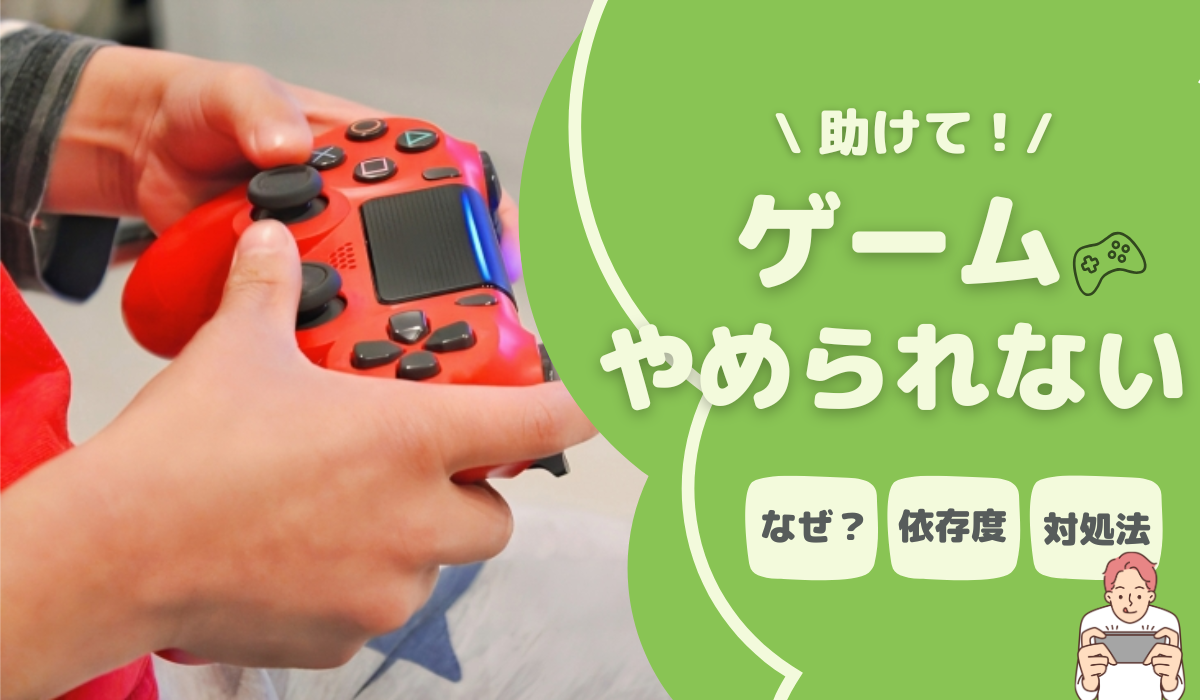ゲームをやめさせるのはどうしたらいい?

「宿題よりゲームばっかり…」「何度言ってもやめない…」
お子さんのゲーム時間、気になっていませんか?
注意すればするほど反発してしまったり、イライラした態度になってしまう…。
子どものゲーム依存を心配する親御さんは年々増えています。
この記事では、療育現場の専門家としての視点から、「ゲームを自分からやめられる」ための声かけや環境づくりについて、わかりやすくお伝えします。
ゲームがやめられなくて困っている・・・こんなお悩みありますよね

-
「あと5分」がいつまでも終わらない
-
ゲームをやめさせようとすると大泣き
-
約束していた時間を守れない
-
宿題やお手伝いよりもゲームを優先してしまう
こうした悩みの背景には、脳のしくみや子どもの発達段階が関係しています。
そもそもなんでゲームって依存性が高いの?
ゲームには、大人でもハマってしまう“しかけ”がたくさんあります。
たとえば:
-
達成感がすぐに得られる(クリアすると褒められる)
-
視覚や音の刺激が強い(ドーパミンが出やすい)
-
終わりがない設計(次のミッション、次のレベルが常にある)
特に発達途中の子どもは「今この瞬間の楽しさ」を優先しがちです。
「切り替えが苦手」「我慢がきかない」といった特性のあるお子さんほど、ゲームから抜け出すのが難しくなります。
小学校から高校生までを対象に一日の平均ゲーム時間を調べてみました
文部科学省や子ども白書などのデータによると、日本の子どもたちの平日の平均ゲーム時間は以下の通りです。
学年別 ゲームの平均時間
| 小学生 | 約90分〜120分 |
| 中学生 | 約120分〜180分 |
| 高校生 | 約180分〜240分 |
さらに、休みの日は倍以上に増えることも珍しくありません。
これを放っておくと、睡眠不足・学力の低下・家族関係の悪化など、生活全体に影響が出てしまいます。
ゲームをやめさせたい!対処法をおしえて!

「じゃあ、どうやってやめさせればいいの?」
一番大切なのは、「やめさせる」ではなく、“自分からやめられる”環境をつくることです。
少しの工夫で「自分」でやめられる!ポイント3つをご紹介!

1. 「終わりの時間」を視覚化しよう
言葉だけで「あと5分」と伝えても、子どもは感覚的に理解しにくいことがあります。
そこでおすすめなのが「タイマー」や「タイムタイマー(時間が色で見える時計)」の活用。
終了時間を目で見てわかるようにすると、納得感が生まれやすくなります。
2. 終了後の“楽しみ”をセットにする
「ゲームが終わったら〇〇しようね」と、やめた後の楽しみを用意しておくと、切り替えがスムーズになります。
たとえば:
-
おやつタイム
-
一緒に散歩やボードゲーム
-
好きな音楽を聴く時間 など
次に楽しいことが待っているという見通しは、ゲームからの切り替えを助けます。
3. 一緒にルールを決める
「親が一方的に決めたルール」は守られにくいもの。
子どもと一緒に話し合って、「1日〇分まで」「終わる〇分前に声をかける」などのルールをつくると、自分で守る意識が育ちます。
ここで大切なのは、叱ることよりも、守れたときにしっかり褒めることです!
他にも工夫はたくさん!
詳しくはそらまめキッズのInstagramを是非ご覧ください(*^^)v
https://www.instagram.com/soramame_kids?igsh=em52NmFuejBlMG5i&utm_source=qr
まとめ
ゲームをやめられないのは、子どもにとって「仕方のないこと」でもあります。
だからこそ、大人が環境を整えたり、見通しを持たせたりすることがカギになります。
🔸タイマーなどで終わりを見える化
🔸終わった後の楽しみを用意
🔸ルールは一緒に作る&褒める
この3つを意識することで、「ゲームをやめさせる」ではなく「自分からやめられる子」に近づいていきます。
無理にやめさせようとするよりも、親子で一緒に試行錯誤する姿勢が、信頼関係を深める一歩になります☆
参考になりましたら嬉しいです♪
 Instagram
Instagram
 TikTok
TikTok
 Note
Note
 Facebook
Facebook