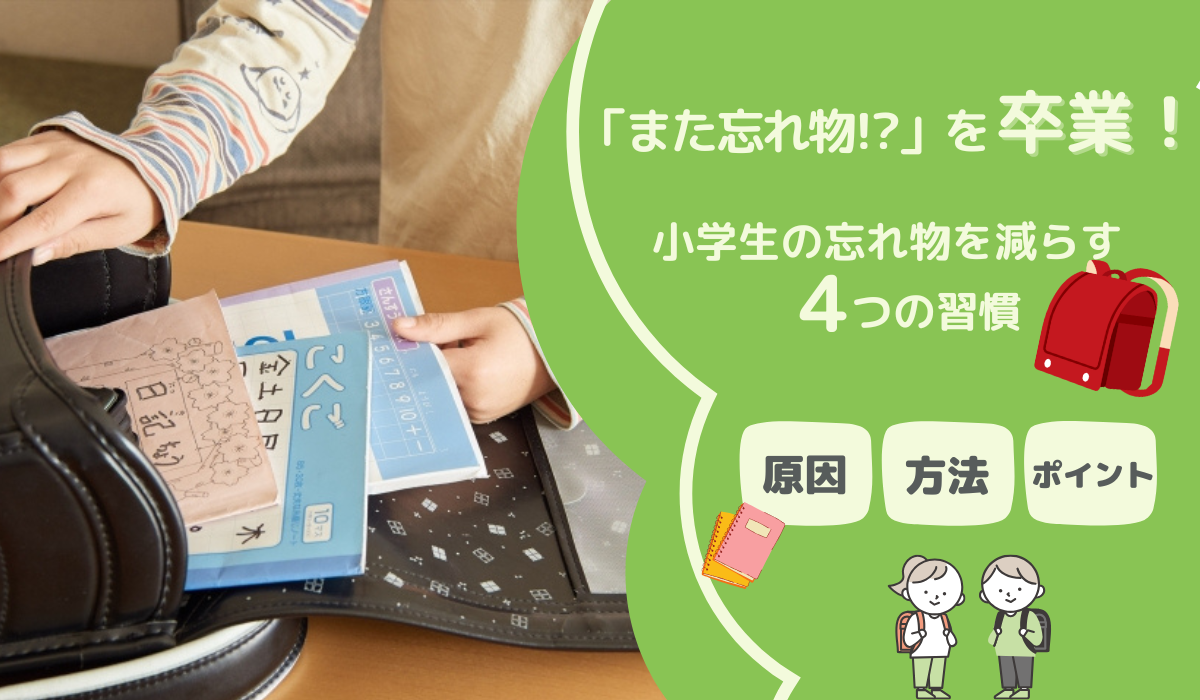はじめに
「また忘れ物!?」――つい声を荒げてしまったことはありませんか?小学生の子どもを持つ保護者にとって、「忘れ物問題」は日常の悩みのひとつです。プリントや給食袋、体操服…持たせたはずなのに、なぜか学校に持って行っていない。子どもを責めたくなる気持ちもわかりますが、実は“忘れ物”には年齢的な発達や心理的な背景が深く関係しています。本記事では、小学生の忘れ物の原因と、それを減らすための具体的な習慣・親の関わり方について、専門的視点を交えながらわかりやすく解説します♪

なぜ忘れ物をするの?その原因と背景を知ろう
年齢による発達段階と記憶力の関係
小学生はまだ脳の発達途中にあり、記憶力や注意力にも成長段階があります。特に低学年の子どもは、短期記憶や作業記憶の容量が小さく、持ち物を思い出す力にムラがあります。「覚えたつもり」でもすぐに忘れてしまうのは自然なことです。また、「持って行くものを思い出す」という行動は、大人にとっては当たり前でも、子どもにとっては高度な自己管理行動。そのため、忘れ物が多いからといって、必ずしも怠慢や不注意とは限りません。発達のステップとして、記憶の補助を活用することが大切です。
環境の変化やストレスも原因に?
子どもは大人以上に、環境の変化や人間関係のストレスに敏感です。進級やクラス替え、担任の変更など、日常の小さな変化でも精神的な負荷がかかり、集中力が低下することがあります。家庭内の雰囲気や兄弟との関係も影響を与えることがあります。こうした背景があると、「忘れ物」は表面的なサインであり、根本には心の不安や緊張がある場合も。子どもの様子がいつもと違うと感じたときは、話を聞く姿勢や安心できる環境づくりを心がけましょう。
「やる気がない」わけじゃない?性格と特性
忘れ物が多い子どもを見ると、「やる気がないのでは?」と心配になる親御さんもいます。しかし、実際には子どもの性格や特性によって、注意が向きにくい・優先順位がつけづらいといった傾向があるかもしれません。感受性が強い子、好奇心旺盛な子、マイペースな子など、それぞれに合ったサポートが必要です。「忘れ物=だらしない」という思い込みは避け、個性として理解し、どうすればうまく付き合えるかを考える視点が重要です。
発達障害(ADHDなど)の可能性も視野に入れて
何度も注意しても忘れ物が改善されず、他にも集中力が続かない、落ち着きがないなどの特性が見られる場合は、ADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害の可能性もあります。ADHDのある子どもは、脳のワーキングメモリや実行機能に課題を抱えており、「やろうとしても忘れてしまう」という状態が日常的にあります。無理に叱っても改善は難しく、環境の工夫や専門的な支援が効果的です。気になる場合は、学校や発達支援センターに相談してみることも検討しましょう。
忘れ物を減らす!今日からできる4つの習慣と実践アイデア
「前日の準備」を親子のルーティンにする
忘れ物対策の第一歩は、朝ではなく「前日夜」の行動にあります。寝る前の5分間を使って、翌日の時間割を見ながら親子で持ち物チェックをする習慣をつけましょう。時間割が見える位置に貼っておくと、子ども自身も確認しやすくなります。親が一緒に「チェックすること」を繰り返すうちに、子どもも自然と覚えていきます。特に低学年のうちは、完全に一人で準備させるのではなく、サポートをしながら“準備する力”を育てることが大切です。

視覚的にわかるチェックリストを活用しよう
文字だけでは記憶が曖昧になりやすい子どもにとって、視覚的なサポートは効果的です。ランドセルの近くに貼る「持ち物チェックリスト」は、写真やイラストつきだとよりわかりやすく、自分で確認する力がつきます。たとえば「筆箱」「水筒」「連絡帳」など、毎日持っていくものをリストにして、準備完了にチェックを入れるのも達成感に繋がります。市販の既製品や100均のホワイトボード、アプリを活用するのもおすすめです。
そらまめキッズおすすめのお仕度ボード♪
◎クツワ こどもの準備ボード トレーニング◎

持ち物の定位置を決めるだけで忘れ物激減!
持ち物の「居場所」が決まっていないと、準備のたびに探すことになり、忘れ物のリスクが上がります。筆箱は机の引き出し、水筒はキッチンカウンターなど、定位置を決めて「使ったら戻す」習慣を意識づけましょう。定位置管理は、子どもが自分で準備を進めるための土台になります。家族でルールを共有しておくと、兄弟がいても混乱せずスムーズです。

一緒に振り返る「帰宅後タイム」で習慣化を促す
忘れ物を減らすには、1日の終わりに「今日どうだった?」と振り返る時間をもつことも効果的です。帰宅後、ランドセルの中を一緒に見ながら、「今日は何を持っていったかな」「明日は何がいるかな」と確認しましょう。この時間はただの確認だけでなく、子どもの考える力や予測力を育てるチャンスでもあります。親子のコミュニケーションにもなり、楽しみながら習慣化につなげることができます。

子どもが自分で準備できるようになる!親の関わり方のポイント
「叱る」より「問いかける」コミュニケーションを
忘れ物をしたとき、つい「なんで忘れたの!?」と叱ってしまいがちですが、叱られると子どもは自信を失いやすくなります。代わりに、「どうすれば思い出せたかな?」「次はどうする?」と問いかけることで、子ども自身に気づきを促し、自主的な行動につながります。叱るよりも、考えさせることが重要です。子どもが自分で答えを見つけられるように、ヒントを出しながら関わると効果的です。

子どもの「できた!」を認めて自信を育てる
忘れ物が減ってきたときは、小さな変化でもしっかり褒めてあげましょう。「自分で準備できたね!」「昨日よりスムーズだったね」と具体的に伝えることで、子どもは達成感を感じ、自信を深めます。自己効力感(やればできるという感覚)が育つと、自発的な行動が増え、準備の習慣が身についていきます。成功体験を積み重ねることが、長期的な成長に繋がります。
忘れ物があっても責めずに、次に活かす会話を
忘れ物をしてしまったときでも、責めるのではなく「どうすれば次はうまくいくかな?」と未来志向の会話を心がけましょう。過去の失敗よりも、次の行動に目を向けることで、子どもは安心して改善に取り組めます。「失敗=学び」という姿勢を家庭内で共有することで、子どももチャレンジする気持ちを持ち続けられます。失敗を恐れず、成長のプロセスと捉えることが大切です。
習慣が身につくまで親が“仕組み”でサポート
子どもが自分で準備できるようになるまでは、親の“仕組みづくり”が必要です。チェックリスト、準備ボックス、視覚サポートなど、環境を整えることで子どもの「できる」が増えていきます。また、親の声かけもルーティン化していくと、徐々にサポートが不要になります。最終的には子どもが一人で準備できることを目標に、段階的に手を離していくのが理想的です。

おわりに
子どもの忘れ物は、ただの“うっかり”ではなく、発達や環境、性格などさまざまな背景が影響しています。「どうしてできないの?」ではなく、「どうやったらできるようになるかな?」という視点に切り替えることで、親子の関係もぐっと良くなります。大切なのは、叱るよりも支えること。今回ご紹介した習慣や声かけを、ぜひ日々の生活に取り入れてみてください。忘れ物が減るだけでなく、子ども自身の自信と自立にもつながります。焦らず、少しずつ、親子で一緒に成長していきましょう。

 Instagram
Instagram
 TikTok
TikTok
 Note
Note
 Facebook
Facebook